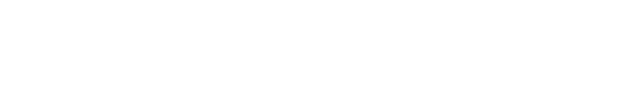脂質異常症
高LDLコレステロール血症
高LDLコレステロール(LDL-C)血症は、血清中のLDL-Cが高値を示す病態であり、動脈硬化症の最も重要な危険因子の1つです。
日本人の高LDL-C血症の頻度は男性で24%、女性で34%以上とされています。
高LDL-C血症はLDL-C値140mg/dL以上と規定されています。
高LDL-C血症の治療目標値は、持っている動脈硬化性疾患の危険因子数により異なり、今後10年間の冠動脈疾患(心筋梗塞など)の発症率により低リスク群から高リスク群に分類されています。
低リスク群はLDL-C 160mg/dL未満、中リスク群は140mg/dL未満、高リスク群は120mg/dL未満、冠動脈疾患の既往のある方は最低でも100mg/dL未満を目標に治療を行います。
診断
診断は、数回の空腹時採血でLDL-Cが高値であることを確認することで行います。
治療
治療は一次予防と二次予防(既に冠動脈疾患の既往のある方)で異なります。
一次予防では、まず生活習慣の改善(食事療法、運動療法、禁煙など)を行い、それでも不十分な場合に薬物療法を併用します。
二次予防の場合(既に冠動脈疾患の既往のある患者)には生活習慣の改善とともに、スタチン系薬剤を中心とした薬物療法を早急に開始します。
生活習慣の改善についてです。
運動療法
運動療法は有酸素運動が有効です。
基本的には、1日合計30分以上、週3回以上、できれば毎日行うことが推奨されます。
持続可能で、ややきつい、もしくは、楽に感じる程度の運動で十分です。
運動の種類としては、速歩、スロージョギング、水泳、サイクリングが行われることが多いです。
食事療法
食事療法は炭水化物摂取をやや少なめにします。
脂肪は、飽和脂肪酸(動物性脂肪に多く含まれる)の摂取量を減らして、魚類などによる不飽和脂肪酸の摂取を増やすようにします。
また、マーガリンなどのトランス脂肪酸を避けます。
野菜、果物、未精製穀類、海藻類、大豆製品などの摂取を増やすことも重要です。
禁煙
禁煙もとても重要です。
喫煙は、すべての動脈硬化性疾患の独立した主要なリスクファクターとなります。
禁煙の効果は、その開始から速やかに現れることもあり、すべての方に勧められます。
体重管理
体重管理に関しては、BMI 25以上を認める方ではBMI 22を目指して、総エネルギー摂取量を減らして、運動を増やすようにします。
これらの食事・運動療法の効果も加わってLDL-C値が正常範囲に十分に入った場合には、薬剤を減量もしくは中止できます。
家族性高コレステロール血症
家族性高コレステロール血症とは、LDL受容体関連遺伝子の変異によって引き起こされる、常染色体優性遺伝形式をとる疾患です。
家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体は200~500人に1人の罹患率を認める比較的頻度の多い疾患です。
若年性の高LDL-C血症、アキレス腱黄色腫、早発性冠動脈硬化症などを認めます。
LDL-Cが180mg/dL以上を認める場合や高LDL-C血症の家族歴を認める場合などは、家族性高コレステロール血症を考慮します。
治療
これらの患者様では、LDL-C 100 mg/dL未満またはLCL-C低下率50%を目標に治療を勧めます。
二次予防の家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体はさらに高リスクと考えられるので70mg/dL未満を目標とします。
治療は、生活習慣の改善と平行して、スタチン系薬剤による加療を行います。
スタチン系薬剤で効果不十分の場合にはレジン、小腸コレステロールトランスポーター阻害薬を併用します。
高中性脂肪(トリグリセライド)血症
高中性脂肪(トリグリセライド)血症(高TG血症)は、10時間以上の空腹時採血の結果、TG値≧150mg/dLを確認して診断します。
随時採血(非空腹時)ではTG値≧175mg/dLで高TG血症と診断します(TG値は食事の影響を受けやすいため)。
基本的に自覚症状は認めず、特定健診や検診時など日常検査で発見されるケースが多いです。
高TG血症には、体質や遺伝子異常に基づいて発症する一次性と、飲酒、肥満、薬剤、糖尿病などによる二次性があります。
高TG血症は動脈硬化性疾患、特に冠動脈疾患発症と関連しているとされています。
したがって、高TG血症に対する主な治療目標は、心血管疾患の進展・発症を予防するためにあります。
すべての患者様において、TG値<150mg/dL(空腹時)、TG値<175mg/dL(随時)とすることが勧められます。
また、著明な高TG血症は、急性膵炎の発症リスクも上昇させるため、TG値≧500mg/dLの際はTG値を積極的に低下させることが推奨されます。
治療
治療は、まず食事療法、運動療法を中心とした生活習慣の改善から開始し、管理不十分の際は薬物治療を考慮します。
生活習慣の改善が治療の基本であり、最も重要なポイントです。
食事療法
食事療法では摂取エネルギーを肥満の有無や活動量に合わせて適正化します。
総エネルギー摂取量(kcal/日)=目標とする体重(kg)×身体活動量(軽い労作で25~30、普通の労作で30~35、重い労作で35~)で算出します。
栄養成分は炭水化物50-60%、脂質25-35%、蛋白質15-20%を基本とし、適宜調整します。
脂肪、特に牛、豚、鳥といった肉類は、脂質異常症の原因となる飽和脂肪酸やコレステロールが多いため、摂取量を控えます。
魚油に含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸のエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)は、TG値を低下させ、さらに血栓予防の効果もあります。
運動療法
運動療法では、毎日軽度から中等度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)を30分以上行うことが望ましいです。
節酒や禁酒
アルコール摂取量が多ければ肝臓でのTG合成が亢進するため、状態に応じて節酒や禁酒とします。
食事療法や運動療法
肥満や内臓脂肪の多い患者様は、食事療法や運動療法により積極的に減量することが推奨されます。
禁煙
喫煙は動脈硬化の確立された危険因子であり全ての方に禁煙を勧めます。
TG値<500mg/dLの場合
TG値<500mg/dLの場合は、まずLDL-Cの管理を優先します。
LDL-Cの管理が不十分であれば、スタチンでの治療が優先となります。
スタチンやエゼチミブにはTG値の低下作用も認められていますが、TG値の管理が不十分であればイコサペント酸エチルやニコチン酸製剤の併用も検討します。
TG値≧500mg/dLの場合
TG値≧500mg/dLでは、急性膵炎の発症リスクが高いことから積極的にTG値を低下させることが推奨され、フィブラート系薬剤を中心として積極的にTG値を低下させます。
いかがでしたでしょうか。
高LDL-C血症や高TG血症を指摘されたことのある方は、是非当院にご相談ください。
頴川博芸 エガワ ヒロキ
浅草橋西口クリニックMo
【経歴】
2016年 東海大学医学部医学科 卒業
2016年 順天堂大学医学部附属静岡病院 臨床研修医室
2017年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 入学
2018年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器・低侵襲外科
2021年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 修了
2021年 越谷市立病院 外科
2022年 順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科・消化器外科
2023年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科
2024年 浅草橋西口クリニックMo院長就任
【資格・所属学会】
日本専門医機構認定 外科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本旅行医学会 認定医
東京都認知症サポート医
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本温泉気候物理医学会
日本腹部救急医学会
日本大腸肛門病学会
順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科 非常勤医師
難病指定医
小児慢性特定疾病指定医