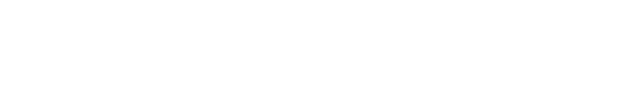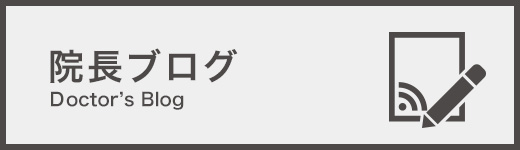インフルエンザ
インフルエンザ
インフルエンザとは
インフルエンザは、ウイルスによって引き起こされる感染症であり、主に冬季に流行します。インフルエンザウイルスは、A型、B型、C型の3つの主要なタイプがありますが、人間に最も重篤な影響を与えるのはA型とB型です。
インフルエンザの症状は、急激な発熱、喉の痛み、筋肉痛、頭痛、倦怠感などが一般的です。また、咳や鼻水も現れることがあります。重症な場合は、肺炎や他の合併症を引き起こす可能性もあります。
感染経路は、感染者からの飛沫感染が主な要因です。くしゃみや咳、話すことによって、ウイルスが空気中に広がり、他の人に感染します。また、直接触れることで感染することもあります。感染を予防するためには、手洗いや咳エチケットの実施、人ごみを避けるなどの対策が重要です。
予防のためには、インフルエンザワクチンの接種が推奨されています。ワクチンは毎年の季節に合わせて製造され、特定のウイルス株に対して免疫を与えることで、感染を予防します。ワクチンは感染を完全に防ぐわけではありませんが、症状の軽減や合併症のリスクの低下に役立ちます。
インフルエンザの症状
-
発熱(高熱): インフルエンザは急激な発熱が特徴で、一般的には38度以上の高い体温が続きます。発熱は突然始まることが多く、数日間続くことがあります。
-
喉の痛み: インフルエンザに感染すると、喉が痛むことがあります。喉の痛みは通常、飲み込む際や話すときに増します。
-
筋肉痛と関節痛: インフルエンザにかかると、全身の筋肉や関節が痛むことがあります。特に背中や四肢の筋肉が痛むことが多いです。
-
頭痛: インフルエンザでは頭痛が生じることがあります。頭痛は重い症状として現れることもあります。
-
倦怠感と体のだるさ: インフルエンザに感染すると、倦怠感や全身のだるさが起こることがあります。これにより、日常活動が困難になることがあります。
-
咳: インフルエンザでは、乾いた咳や痰が生じることがあります。咳は比較的早い段階から現れることがあります。
-
鼻づまりや鼻水: 一部のインフルエンザ感染者は、鼻づまりや鼻水を経験することがあります。
インフルエンザの感染経路と予防法
感染経路:
- 飛沫感染: 感染者がくしゃみや咳をするときに、ウイルスが空気中の飛沫として広がります。これらの飛沫を他の人が吸い込むことで感染が広がります。
- 直接接触感染: 感染者の口や鼻から出たウイルスに触れ、その後自分の目や口、鼻などに触れることで感染が起こります。例えば、感染者の手との直接的な接触や、感染した表面に触れることが原因となります。
予防法:
-
ワクチン接種: インフルエンザワクチンは感染を予防するために効果的な方法です。ワクチンは毎年の季節に合わせて製造され、特定のウイルス株に対して免疫を与えることで感染を予防します。定期的なワクチン接種が推奨されます。
-
手洗いと咳エチケットの実施: 頻繁な手洗いは感染の予防に非常に重要です。石けんと水を使って手をしっかりと洗い、20秒以上こすり洗いを行いましょう。また、咳やくしゃみをする際には、ティッシュや袖の内側を使って口や鼻を覆いましょう。使用したティッシュはすぐに捨て、手洗いを行います。
-
人ごみを避ける: インフルエンザは感染者との接触によって広がることが多いため、人ごみや密集した場所を避けることが予防に役立ちます。
-
マスクの着用: インフルエンザ流行時や感染のリスクが高い状況では、マスクの着用が推奨されます。マスクは飛沫感染を軽減する効果があります。
-
健康な生活習慣の維持: 充分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、健康な生活習慣を維持することで免疫力を高めることができます。これにより、感染症に対する抵抗力が向上します。
これらの予防法を実施することで、インフルエンザの感染リスクを減らすことができます。特に、ワクチン接種は効果的な予防方法とされていますので、定期的な接種を受けることをおすすめします。
インフルエンザウイルスの特徴
-
ウイルスのタイプ: インフルエンザウイルスは、A型、B型、C型の3つの主要なタイプが存在します。人間に最も重篤な影響を与えるのはA型とB型です。A型は多くの種類の動物に感染し、人間にも感染するため、大規模な流行やパンデミックを引き起こす可能性があります。
-
遺伝子の変異性: インフルエンザウイルスは、遺伝子の変異が頻繁に起こる特徴があります。これにより、ウイルスの特性や抗原性が変化し、ワクチンの効果や免疫の獲得に影響を与えます。特にA型インフルエンザウイルスは、遺伝子の再組み合わせや変異により新しい亜型が生まれることがあり、新型インフルエンザの発生源となることがあります。
-
呼吸器への感染: インフルエンザウイルスは、主に呼吸器を通じて感染します。感染者がくしゃみや咳をするときに、ウイルスが空気中の飛沫として広がり、他の人が吸い込むことで感染が広がります。また、直接触れることによっても感染することがあります。
-
季節性と流行: インフルエンザは季節性の病気であり、特に冬季に流行する傾向があります。寒冷な気候や密集した環境が感染拡大を促進する要因とされています。また、ウイルスの変異や新しい亜型の出現により、大規模な流行やパンデミックが発生することもあります。
-
症状の多様性: インフルエンザの症状は個人によって異なる場合がありますが、一般的には急激な発熱、喉の痛み、筋肉痛、頭痛、倦怠感などが現れます。また、咳や鼻水も生じることがあります。重症な場合は、肺炎や他の合併症を引き起こす可能性があります。
インフルエンザの流行と予防対策
インフルエンザの流行について
-
季節性の流行: インフルエンザは季節性の病気であり、特に冬季に流行する傾向があります。寒冷な気候や人々が密集している場所での感染拡大が主な要因です。一般的には10月から始まり、ピークは12月から2月にかけてとされていますが、地域や年によって変動する場合もあります。
-
パンデミック: インフルエンザウイルスは遺伝子の変異や再組み合わせにより、新しい亜型が発生することがあります。新型のインフルエンザウイルスが人間に感染し、世界的な流行が起こる場合をパンデミックと呼びます。過去には1918年のスペイン風邪や2009年の新型H1N1インフルエンザがパンデミックを引き起こしました。
-
ウイルスの変異と予防ワクチン: インフルエンザウイルスは遺伝子の変異が頻繁に起こり、新しいウイルスの亜型が生まれることがあります。このため、毎年のワクチンは予測される亜型に基づいて製造されます。しかし、ウイルスの変異が予測を超える場合もあり、ワクチンの効果が制限されることがあります。
-
感染拡大の予測と監視: インフルエンザの流行を監視するため、世界中の機関や組織が監視体制を構築しています。これには、ウイルスの型やサブタイプの監視、感染症報告、病院や医療機関からのデータ収集などが含まれます。これにより、流行の予測や対策の立案が行われます。
-
感染予防の啓発と対策: インフルエンザの流行期には、感染予防の啓発活動が行われます。これには手洗いの重要性、咳エチケットの実施、マスクの着用、ワクチン接種の呼びかけなどが含まれます。また、学校や職場などでの集団感染を防ぐための対策も行われます。
インフルエンザの流行は年によって異なる場合があります。地域ごとの状況や予防対策の効果によっても変動するため、公共衛生機関の指示や最新の情報に基づいて対策を行うことが重要です。
インフルエンザの予防策とワクチン接種
予防策:
-
ワクチン接種: インフルエンザワクチンは感染を予防するために効果的な方法です。ワクチンは毎年の季節に合わせて製造され、特定のウイルス株に対して免疫を与えることで感染を予防します。一般的にはワクチン接種が最も効果的な予防策とされています。
-
手洗いと咳エチケットの実施: 頻繁な手洗いは感染の予防に非常に重要です。石けんと水を使って手をしっかりと洗い、20秒以上こすり洗いを行いましょう。また、咳やくしゃみをする際には、ティッシュや袖の内側を使って口や鼻を覆いましょう。使用したティッシュはすぐに捨て、手洗いを行います。
-
人ごみを避ける: インフルエンザは感染者との接触によって広がることが多いため、人ごみや密集した場所を避けることが予防に役立ちます。特に流行期や感染のリスクが高まっている場合は、人混みを避けるようにしましょう。
-
マスクの着用: インフルエンザ流行時や感染のリスクが高い状況では、マスクの着用が推奨されます。マスクは飛沫感染を軽減する効果があり、自身の感染リスクや他人への感染リスクを減らすことができます。
-
健康な生活習慣の維持: 充分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、健康な生活習慣を維持することで免疫力を高めることができます。免疫システムが強化されることで、感染症への抵抗力が向上します。
ワクチン接種: ワクチン接種はインフルエンザの予防に非常に効果的な方法です。以下の点について注意してください。
-
定期的な接種: インフルエンザワクチンは毎年の季節ごとに接種する必要があります。ワクチンは季節性の流行を予防するために製造されるため、毎年の定期接種が推奨されます。
-
グループ別の優先順位: ワクチンの供給が限られている場合、高リスクグループ(高齢者、基礎疾患を持つ人、妊婦など)が優先的に接種を受ける場合があります。地域のガイドラインや医療機関の指示に従って接種のスケジュールを確認しましょう。
-
効果と副作用: インフルエンザワクチンは一般的に効果的で安全なワクチンですが、個人によって副作用が現れる場合があります。接種前に医療機関に相談し、自身の健康状態やアレルギーの有無を共有しましょう。
-
接種タイミング: インフルエンザワクチンの効果が現れるまでには数週間かかることがあります。流行の前に接種することが推奨されますが、遅れて接種する場合でも感染を予防する効果があります。
インフルエンザ対策のための呼吸衛生
インフルエンザ対策の一環として、呼吸衛生が非常に重要です。以下に呼吸衛生のポイントを説明します。
-
咳エチケットの実施: 咳やくしゃみをする際には、口や鼻を覆うためにティッシュや袖の内側を使いましょう。ティッシュを使用した場合は、すぐに捨てて適切な手洗いを行います。口や鼻を手で覆わないようにし、飛沫感染のリスクを軽減します。
-
マスクの着用: インフルエンザの流行期や感染リスクの高い場所では、マスクの着用が推奨されます。マスクは飛沫を防ぎ、感染のリスクを減らす効果があります。正しく着用し、口と鼻を覆うようにしましょう。
-
適切な手洗い: インフルエンザの予防には、頻繁な手洗いが重要です。石けんと水を使って手をしっかりと洗い、20秒以上こすり洗いを行います。特に外出先から帰った後、トイレ使用後、食事前後など、適切なタイミングで手洗いを行いましょう。
-
こまめな換気: 閉めきった空間ではウイルスが滞留しやすくなるため、こまめな換気が必要です。室内の空気を入れ替えるために、定期的に窓を開けたり、換気システムを活用しましょう。
これらの呼吸衛生対策は、感染症の予防に役立ちます。特に感染リスクの高い場所や季節には、積極的に実施することが重要です。
診断
インフルエンザ様症状やインフルエンザらしい病歴があり、迅速診断キットが陽性なら診断確定です。
インフルエンザを強く疑われますが、迅速診断テストが陰性で、検査による診断を確定する必要がある場合は、半日~1日ぐらい時間を空けて迅速診断テストを再検することもあります。
特に発症12時間以内は偽陰性が多くなるとされています。
検査感度が高い適切な鼻咽頭スワブ検体採取のために、スワブ先端を鼻咽頭後壁に当てて数秒間挿入しスワブを数回回転させる方法が推奨されています。
インフルエンザ流行期や接触者でのインフルエンザ様症状では、迅速診断キットでの偽陰性の件数が増えるため、迅速診断キットを省略して診断することも考慮します。
経過
インフルエンザは自然に治癒します。
健常者では平均的には3~4日で解熱し、長くても1週間以内に軽快します。
また、咳・痰・鼻水といった上気道症状は、週単位で遷延することがたまにあります。
治療
治療の基本は抗インフルエンザ薬です。
特に心・肺・肝・腎疾患、糖尿病、肥満、免疫不全、ステロイド剤/免疫抑制剤使用、進行悪性腫瘍などの合併症リスクのある患者様や2歳未満の乳幼児、65歳以上の高齢者、妊婦、入院中の患者様には、インフルエンザ発症から48時間以内の抗インフルエンザ薬の開始が推奨されます。
これらのリスク因子がない場合でも、発症2日以内の患者様、有効性と副作用を理解している患者様、発症患者様のご家族に合併症と状態悪化のリスクがある場合などで抗インフルエンザ薬投与を考慮します。
抗インフルエンザ薬は、発症から48時間以内に開始すると、解熱と症状軽快を早めることが可能です。
一方、発症48時間以降の有用性は乏しいとされています。
適応は、高齢者(65歳以上)、乳幼児(2歳未満)、心疾患・肺疾患・肝疾患・腎疾患・糖尿病・免疫不全、悪性腫瘍、神経疾患、病的肥満などの基礎疾患を認める患者様、ステロイド/免疫抑制剤使用している患者様、入院している患者様の場合は、抗インフルエンザ薬投与を積極的に考慮します。
妊婦(産後2週間含む)の方も合併症のリスクが高くなるため、抗インフルエンザ薬のよい適用です。
重篤な合併症を来すリスクがある場合は、診断を待たずに治療を始めることも検討します。
効果としては、インフルエンザ発症から48時間以内の投与開始で、有症状期間が1日前後短縮されます。
対症療法としてはアセトアミノフェンを用います。
小児のインフルエンザに対しては、アスピリンや非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)の投与は原則避けます。
成人のインフルエンザでも、これらの処方による中枢神経合併症の増加や予後不良の根拠はありませんが、理論的なリスクから、解熱鎮痛薬としてはアセトアミノフェンを使用することが無難とされています。
予防投与
インフルエンザ曝露後の予防投与の適応は、集団発生の規模、対象者の職種や基礎疾患などさまざまな要素をもって検討します。
特に、インフルエンザ発症による、合併症や重症度や死亡率でのリスクがあると考えられる曝露された方(心・肺・肝・腎疾患、糖尿病、肥満、免疫不全、ステロイド剤/免疫抑制剤使用、進行悪性腫瘍などの合併症リスクのある患者様や2歳未満の乳幼児、65歳以上の高齢者、妊婦、入院中の患者様)については、オセルタミビルまたはザナミビルの予防投与を考慮します。
新型コロナウイルスとの違い
典型的なインフルエンザでは、新型コロナウイルスと比べて、最初の発熱が急激で咽頭痛、鼻水・鼻づまり、咳などの上気道症状がやや遅れて出現する傾向が強いですが、新型コロナウイルスでも初期症状が急激に出る場合があり、症状だけでの厳密な区別は難しいです。
しいてあげるなら、インフルエンザでは味覚・嗅覚障害を来さないので、味覚嗅覚障害が明らかな場合はインフルエンザの可能性が低く、新型コロナウイルスの可能性が高いといえます。
インフルエンザについてよくある質問と回答
Q: インフルエンザと風邪の違いは何ですか?
A: インフルエンザと風邪は、共に呼吸器感染症ですが、症状や重症度に違いがあります。インフルエンザは急激な発症と高熱が特徴で、全身的な倦怠感や筋肉痛が現れることが多いです。一方、風邪はより軽度で、鼻水や鼻づまり、のどの痛みなどが主な症状となります。
Q: インフルエンザワクチンはどのくらい効果的ですか?
A: インフルエンザワクチンは季節性インフルエンザウイルスに対する効果がありますが、ウイルスの変異やマッチングの問題により、効果は年によって異なることがあります。ワクチンは感染を完全に防ぐわけではありませんが、感染のリスクを軽減し、症状の重症化や合併症の発生を予防する効果があります。
Q: インフルエンザに感染した場合、どのくらいの期間病気を引き起こしますか?
A: 通常、インフルエンザに感染すると、症状が現れるまでの潜伏期間は1〜4日程度です。感染後、症状は通常1週間程度続きますが、個人によって異なることがあります。症状が消えた後も体力が回復するまで時間がかかる場合があります。
Q: インフルエンザワクチンは誰に推奨されていますか?
A: インフルエンザワクチンは基本的には誰にでも推奨されますが、特に高リスクグループの方々には強く推奨されています。高齢者、妊婦、基礎疾患を持つ人、医療従事者などが該当します。
Q: インフルエンザに感染しないための予防策はありますか?
A: インフルエンザ感染を予防するためには、以下の予防策を実践することが重要です。手洗いの徹底、マスクの着用、人ごみの回避、咳エチケットの実施、適切な栄養や睡眠の確保などが挙げられます。また、ワクチン接種も感染リスクを軽減するための重要な手段です。
いかがでしたでしょうか。
当院では発熱外来を行っておりますので、インフルエンザを疑うような症状が出現した場合は、是非当院にご相談ください。
頴川博芸 エガワ ヒロキ
浅草橋西口クリニックMo
【経歴】
2016年 東海大学医学部医学科 卒業
2016年 順天堂大学医学部附属静岡病院 臨床研修医室
2017年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 入学
2018年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器・低侵襲外科
2021年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 修了
2021年 越谷市立病院 外科
2022年 順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科・消化器外科
2023年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科
2024年 浅草橋西口クリニックMo院長就任
【資格・所属学会】
日本専門医機構認定 外科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本旅行医学会 認定医
東京都認知症サポート医
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本温泉気候物理医学会
日本腹部救急医学会
日本大腸肛門病学会
順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科 非常勤医師
難病指定医
小児慢性特定疾病指定医