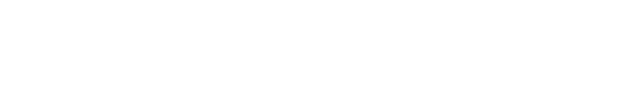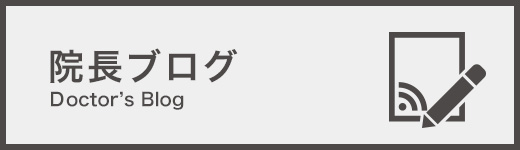新型コロナウイルス
新型コロナウイルスについての基本情報
新型コロナウイルスとは
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、2019年に中国で最初に確認されたウイルスで、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)という病気を引き起こす原因となります。新型コロナウイルスは、人から人への接触や飛沫感染によって広まります。
このウイルスは、呼吸器系に影響を与え、咳やくしゃみなどの感染者の飛沫から他の人に感染することがあります。感染者の症状には、発熱、咳、呼吸困難、倦怠感などがありますが、感染した人の中には無症状の場合もあります。
COVID-19は、軽度の風邪症状から重症の肺炎、呼吸不全、死亡に至ることもあります。特に高齢者や基礎疾患を持つ人々、免疫力が低下している人々にとって重篤な病気となることが多いです。
祖先株Wuhan-1から変異株として、日本では2021年5月にアルファ株、2021年8月下旬にデルタ株、2022年2月からB.1.1.529(オミクロン株)と変遷しています。
日本ではオミクロン株は2022年2月からBA.1株からBA.2株に置き換わり、2022年7月以降はBA.5株が主流となっています。
2022 年 12 月以降、世界で検出されるウイルスのほぼすべてがオミクロンと考えられています.
新型コロナウイルスの特徴と感染経路
特徴:
- 呼吸器感染症: 新型コロナウイルスは主に呼吸器系に影響を与えます。感染した人は咳やくしゃみによってウイルスを含んだ飛沫を放出し、他の人に感染させる可能性があります。
- 高い感染性: 新型コロナウイルスは非常に感染性が高く、人から人への広がりが速い特徴があります。感染力は、他のコロナウイルス(通常の風邪を引き起こすコロナウイルス)よりも強いとされています。
- 潜伏期間: 感染から症状が現れるまでの潜伏期間は、オミクロン株では2-3日とされており、曝露から7日以内に約94%が発症します。感染した人は潜伏期間中でも他の人にウイルスを感染させることがあります。
感染経路:
- 飛沫感染: 感染者が咳やくしゃみをするときに放出される飛沫が、近くの人の口や鼻、目の粘膜に付着し、感染が起こります。これが最も一般的な感染経路です。
- 接触感染: 感染者がウイルスに触れた手で、口や鼻、目などの粘膜を触れることによって感染が広がります。
- 空気感染: 閉鎖空間や換気の悪い場所で、感染者が放出した微小な飛沫が空中に浮遊し、他の人が吸い込むことによって感染が起こることもあります。ただし、この感染経路は主に密閉された環境での長時間の接触で起こる可能性が高いとされています。
感染経路は、主に人と人の接触や近距離での飛沫感染が主要です。そのため、マスクの着用、適切な手洗い、社会的距離の確保、十分な換気などの予防策が重要とされています。
新型コロナウイルスの症状と進行
新型コロナウイルス感染の一般的な症状
新型コロナウイルス感染の一般的な症状は以下のようなものですが、注意点として個人によって症状の程度や現れ方が異なる場合があります。また、軽症の場合や無症状の場合もあります。
一般的な症状:
- 発熱: 37.5度以上の体温の上昇が見られることがあります。
- 咳: 乾いた咳や喉の痛みが現れることがあります。
- 倦怠感: 疲労感や体のだるさが感じられることがあります。
- 呼吸困難: 呼吸が苦しく感じることや息切れが起こることがあります。
- 喉の痛み: 喉の痛みや咳嗽(せき)が現れることがあります。
- 鼻づまり: 鼻づまりや鼻水が出ることがあります。
- 味覚・嗅覚の喪失: 食べ物の味や臭いが感じられないことがあります。
これらの症状がある場合は、新型コロナウイルス感染の可能性があります。また、重症化する可能性もあるため、症状が進行した場合は早めに医療機関に相談することが重要です。
新型コロナウイルス感染の進行と重症化リスク
新型コロナウイルス感染の進行と重症化リスクは、個人の免疫状態や基礎疾患の有無、年齢などさまざまな要素に影響されます。
一般的な進行のパターン:
-
軽症: 大部分の感染者は軽い症状で経過し、自宅での自己管理が可能です。熱や咳などの一般的な風邪症状が見られることが多いです。
-
中等症: 一部の感染者は呼吸困難や酸素不足などの症状が現れる場合があります。入院治療が必要なケースもありますが、一般的には軽度の酸素補給や対症療法が行われます。
-
重症: 重症化した場合は、重篤な呼吸困難や肺炎が進行することがあります。集中治療室(ICU)や人工呼吸器の使用が必要となる場合があります。
重症化リスクの高い人々:
重症化のリスク因子としては以下のものが挙げられます。
※出典:2023 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 9.0 版」
これらの重症化リスクをお持ちの方で、新型コロナウイルス感染症を発症した方は、新型コロナウイルス治療補助薬の適応となる可能性があります。早めに当院内科にご相談ください。
診断と検査方法
新型コロナウイルス感染症の診断と検査には、主に以下の方法が使用されます。
-
PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応検査): PCR検査は、新型コロナウイルスの遺伝子を検出するための検査方法です。この検査は、鼻や喉の粘膜からの検体を採取し、ウイルスのRNA(リボ核酸)を増幅して検出します。PCR検査は感染の早期段階での診断に有効です。
-
迅速抗原検査: 迅速抗原検査は、新型コロナウイルスの抗原(ウイルスの一部)を検出するための検査方法です。この検査はPCR検査よりも迅速に結果を得ることができますが、感度や特異度はPCR検査に比べて低い場合もあります。
重症度
重症度は以下のように分類されます。
※出典:2023 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 9.0 版」
後遺症
新型コロナウイルス感染症の後遺症はlong Covid、long-haul Covid、post Covid-19 conditionと呼ばれています。
感染後3カ月以内に発症し、少なくとも2カ月続くが、他の病気で説明できない症状を指すとされています。
症状で最も多いのは倦怠感、呼吸困難、認知機能障害、胸痛、嗅覚障害、味覚障害、動悸などであり、日常生活に影響を及ぼしています。
これらの後遺症は自宅隔離やホテル療養者など、医療機関を満足に受診できなかった患者様に多く見受けられます。
発症から約2カ月で48%、約4カ月で27%に後遺症を認めるとされています。
また、全体の24%の患者様に脱毛が認められています。
インフルエンザとの違い
インフルエンザとの違いを下図に示します。
|
|
新型コロナ |
|
|---|---|---|
|
感染予防策 |
飛沫、接触 |
飛沫、接触 |
|
ウイルス排出期 |
発症2日前から10日以内 |
発症直後から5~10日間 |
|
ウイルス排出のピーク |
発症1日前 |
発症2~3日後 |
|
潜伏期間 |
2~14日(中央値5日) |
1~4日(中央値2日) |
|
症状の持続 |
2~3週間 |
3~7日 |
|
死亡率 |
0.25~3% |
0.1% |
|
発熱 |
〇 |
◎ |
|
咳 |
〇 |
◎ |
|
咽頭痛 |
〇 |
◎ |
|
頭痛 |
〇 |
◎ |
|
鼻水 |
〇 |
〇 |
|
味覚・嗅覚障害 |
〇 |
△ |
5類感染症への移行
新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日から5類感染症へと移行しました。
5類感染症化による影響
- 患者様への公費支援の大部分が終了。
- 感染症法による入院措置と行政による入院調整の終了。
- ホテル療養の終了。
- 療養中の行動制限の緩和。
感染者の自宅療養期間は?
- 外出を控えるかどうかは個人の判断にゆだねられる。
- 外出を控えることが推奨される期間:発症後5日間(特に感染させるリスクが高いため)、かつ、症状改善から24時間以上経過。
- 発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨(強制ではない)。
- 濃厚接触者への制限はなし。
基本的な感染対策
基本的な感染対策については今までとほとんど変わりません。
- 新型コロナウイルスワクチン(3回以上、オミクロン対応2価ワクチン)
- 換気の悪い屋内や人混みでのマスク着用
- 換気
- 身体的距離の確保(最低1m、可能なら2m)
- 手指衛生(アルコール製剤、または、流水と石鹸)
- 換気の悪い3密(密集・密接・密閉)の回避
- 体調不良時は受診以外で外出しない、人と会わない
いかがでしたでしょうか。
新型コロナウイルスにかかる可能性は常に存在しており、かぜやインフルエンザと症状に大きな違いはなく、診断には未だ検査が必須と言える状況です。
発熱や風邪症状などのある方は、是非当院発熱外来を受診ください。
頴川博芸 エガワ ヒロキ
浅草橋西口クリニックMo
【経歴】
2016年 東海大学医学部医学科 卒業
2016年 順天堂大学医学部附属静岡病院 臨床研修医室
2017年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 入学
2018年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器・低侵襲外科
2021年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 修了
2021年 越谷市立病院 外科
2022年 順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科・消化器外科
2023年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科
2024年 浅草橋西口クリニックMo院長就任
【資格・所属学会】
日本専門医機構認定 外科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本旅行医学会 認定医
東京都認知症サポート医
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本温泉気候物理医学会
日本腹部救急医学会
日本大腸肛門病学会
順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科 非常勤医師
難病指定医
小児慢性特定疾病指定医