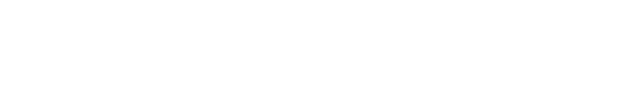高血圧
本態性高血圧
日本で高血圧のある方は約4,300万人と推定されています。
治療の目標は、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患の発症予防や、それによる身体機能障害の発症・進展、死亡を抑制することにあります。
患者様それぞれの病態に応じて降圧目標の値が設定されています。
高リスクな方ほど、厳格な降圧が重要です。
診断
まず、診察室血圧(医療機関で測った血圧)が140/90mmHg以上、家庭血圧(自宅で測った血圧)の平均が135/85mmHg以上で高血圧症の診断となります。
高血圧にはいわゆる生活習慣病に属する『本態性高血圧』と、他の病気に由来する『二次性高血圧』に分かれます。
ほとんどが本態性高血圧ですが、二次性高血圧が疑わしい場合にはそれを診断して治療する必要があります(詳細は後述)。
成人における高血圧の分類
|
分類 |
診察室血圧(mmHg) |
家庭血圧(mmHg) |
||
|---|---|---|---|---|
|
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
|
|
正常血圧 |
<120 かつ <80 |
<115 かつ <75 |
||
|
正常高値血圧 |
120-129 かつ <80 |
115-124 かつ <75 |
||
|
高値血圧 |
130-139 かつ/または 80-89 |
125-134 かつ/または 75-84 |
||
|
Ⅰ度高血圧 |
140-159 かつ/または 90-99 |
135-144 かつ/または 85-89 |
||
|
Ⅱ度高血圧 |
160-179 かつ/または 100-109 |
145-159 かつ/または 90-99 |
||
|
Ⅲ度高血圧 |
≧180 かつ/または ≧110 |
≧180 かつ/または ≧110 |
||
|
収縮期高血圧 |
≧140 かつ <90 |
≧135 かつ/または <85 |
||
複数回の血圧測定でも高血圧が認められず、家庭血圧でも高血圧を認めない場合には、高血圧ではないといえます。
診察室や健康診断で血圧が高い場合でも、家庭での測定でそれぞれの高血圧の基準値を下回る場合は白衣高血圧と診断され、臓器合併症がないことが確認できれば、高血圧発症早期発見のため経過観察は必要なものの、治療は必要ありません。
治療
下図に高血圧の治療目標値を記載します。
降圧目標
|
|
診察室血圧(mmHg) |
家庭血圧(mmHg) |
|---|---|---|
|
75歳未満の成人 |
<130/80 |
<125/75 |
|
脳血管障害患者 |
||
|
冠動脈疾患患者 |
||
|
慢性腎臓病患者(蛋白尿+) |
||
|
糖尿病患者 |
||
|
抗血栓薬内服中 |
||
|
75歳以上の高齢者 |
<140/90 |
<135/85 |
|
慢性腎臓病患者(蛋白尿―) |
治療の基本は、生活習慣の改善(減塩、食指指導、減量、運動、節酒、禁煙)と降圧薬による加療です。
まず、すべての高血圧の方に対して、この生活習慣の修正が必要となります。
減塩は食塩1日6g未満を目指します。
食事指導に関しては、野菜・果物・魚を積極的に摂取してコレステロールの少ない食事を試みます。
体重はBMI 25未満を目標とします。体重1kgあたり血圧が1mmHg程度下がるともいわれています。
運動は、1日30分以上の有酸素運動を目安に行います。
節酒に関しては、男性でエタノール換算20~30mL/日、女性でエタノール換算10~20mL/日以下を目安します。なお、エタノール換算20~30mLは、日本酒1合、ビール中瓶1本、ワイン2杯、ウイスキー1杯程度に相当します。
禁煙は高血圧の方では特に積極的に試みていただきます。
生活習慣を修正したうえで、かつ、3剤以上の適切な用量の降圧薬を継続投与しても、目標血圧に達しない状態を「治療抵抗性(難治性)高血圧」と呼びます。
この場合、まずきちんと降圧薬を内服できているかを確認します。
その次に二次性高血圧を疑い、調べていきます(後述)。
二次性高血圧
本態性高血圧の診断には二次性高血圧の除外が必須となります。
腎実質性高血圧、腎血管性高血圧、甲状腺疾患、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、薬剤誘発性高血圧、睡眠時無呼吸症候群が頻度が高いです
特に、治療抵抗性の高血圧、急激な高血圧の発症、若年発症の高血圧では、二次性高血圧を調べます。
腎実質性高血圧
腎実質性高血圧は、腎臓の実質障害に基づく高血圧で、二次性高血圧の中で頻度が高い疾患の1つです。
高血圧全体の2~5%を占めるとされています。
高血圧を認める患者様で、糖尿病性腎症・慢性糸球体腎炎・腎硬化症・多発性囊胞腎など腎機能障害を来す疾患を認めた場合に診断となります。
腎血管性高血圧
腎血管性高血圧は、腎動脈の狭窄・閉塞の結果、レニン・アンジオテンシン(RA)系を賦活することにより高血圧を来す疾患です。
高血圧全体の約1%程度を占めるといわれています。
RA系阻害薬投与後の急激な腎機能の悪化や腹部エコーなどで腎臓のサイズに左右差を認める場合などに疑います。
診断は、画像検査で腎動脈の狭窄を認めることと、機能試験で腎臓からのレニンの過剰分泌を証明することです。
片側性の腎血管性高血圧では、RA系阻害薬を中心に、β遮断薬やCa拮抗薬、利尿薬などの降圧薬を組み合わせて、注意深く治療していきます。
一方、両側性の腎血管性高血圧では、RA系阻害薬は急激な腎機能障害を来す可能性があるため禁忌とされています。
原発性アルドステロン症
原発性アルドステロン症はアルドステロン産生腫瘍または副腎の過形成による特発性アルドステロン症を来たし、血中のアルドステロン濃度が上昇することにより高血圧を来す疾患です。
原発性アルドステロン症は高血圧全体の5~15%を占めるされています。
II度以上の高血圧、副腎偶発腫瘍合併例、治療抵抗性の高血圧、低K血症などの所見を認めるときは検査を行うことが推奨されます。
診断は、まず血漿レニン活性と血漿アルドステロン濃度比などによりスクリーニング検査を行い、これらのいずれかの検査にて陽性を認める場合に、カプトプリル試験などの機能確認検査をで行うことによりなされます。
片側性の病変では、腹腔鏡下副腎摘出術が第1選択となります。
両側性や手術困難例などではミネラルコルチコイド受容体拮抗薬および他の降圧薬にて治療を行います。
クッシング症候群
クッシング症候群とは、コルチゾールの過剰産生により、満月様顔貌、野牛肩、中心性肥満と四肢近位筋萎縮、皮膚菲薄化、赤色皮膚線条、皮下出血斑などの特徴的な身体所見(クッシング徴候)を呈する疾患群です。
コントロール不良な高血圧・糖尿病、低K血症、副腎偶発腫瘍、特徴的身体所見(クッシング徴候)、病的骨折や著しい骨粗鬆症がみられる場合に本症を疑います。
クッシング症候群を疑った場合は、早朝空腹安静時の血中ACTHとコルチゾールを測定し、コルチゾール高値と日内変動(8時、21時)の消失を証明し、画像検査で病変部位を確認します。
治療は、原因によります。
副腎腺腫を認める場合は手術を、クッシング病では経蝶形骨洞化下垂体摘出術、異所性ACTH産生腫瘍では腫瘍摘出術などを行います。
褐色細胞腫
褐色細胞腫とは、副腎髄質に由来するカテコラミン産生性神経内分泌腫瘍です。
頭痛、蒼白などのカテコラミン過剰症状伴う高血圧や発作性の高血圧を認める場合に疑います。
スクリーニング検査として、尿中・血中カテコラミン濃度を測定します。
治療は腫瘍を切除することです。
睡眠時無呼吸症候群
閉塞性睡眠時無呼吸症候群とは、いびきや睡眠中の無呼吸、日中の眠気などを呈する疾患です。
血圧の変動を伴う夜間高血圧を示すことが多く、早朝高血圧を認める患者では積極的に疑います。
また、身体所見上は昼間の眠気、夜間頻尿、夜間呼吸困難などを認める場合にも疑います。
確定診断は、睡眠検査により行います。
治療は体重減量とCPAP療法です。
CPAP療法によって降圧が測れない場合は、降圧薬による治療を開始し、積極的に夜間高血圧の改善を試みます。
薬剤誘発性高血圧
NSAIDs、甘草を含む漢方薬、ステロイド、エリスロポエチン、シクロスポリン、エストロゲン(特に経口避妊薬)、三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、MAO阻害薬、抗VEGF抗体薬などは高血圧を来すことが知られています。
これらの薬剤を内服している場合には可能な限り中止を考慮します。
薬剤中止が困難な場合は、Ca拮抗薬、ACE阻害薬/ARB、利尿薬などの薬剤を用いて降圧に努めます。
甲状腺機能亢進症・低下症
動悸、倦怠感などの症状を認める場合や脈圧が極度に大きかったり小さかったりした場合に疑います。
いかがでしたでしょうか。
高血圧を指摘されたことがある方は、是非当院にてご相談ください。
頴川博芸 エガワ ヒロキ
浅草橋西口クリニックMo
【経歴】
2016年 東海大学医学部医学科 卒業
2016年 順天堂大学医学部附属静岡病院 臨床研修医室
2017年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 入学
2018年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器・低侵襲外科
2021年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 修了
2021年 越谷市立病院 外科
2022年 順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科・消化器外科
2023年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科
2024年 浅草橋西口クリニックMo院長就任
【資格・所属学会】
日本専門医機構認定 外科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本旅行医学会 認定医
東京都認知症サポート医
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本温泉気候物理医学会
日本腹部救急医学会
日本大腸肛門病学会
順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科 非常勤医師
難病指定医
小児慢性特定疾病指定医