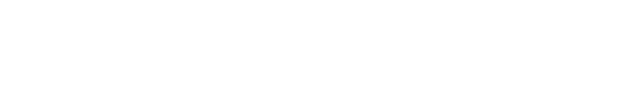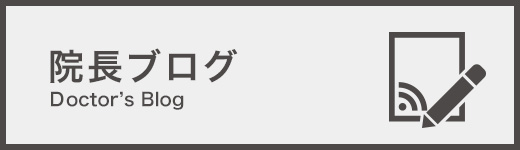粉瘤を治療せず放置するリスクとは?取らないとどうなるのか
「粉瘤を放置したらどうなるの?」「粉瘤を放置するリスクが知りたい」と思っていませんか?
粉瘤とは皮膚にできる良性の腫瘍で、基本的には痛みを伴いません。そのため放置してしまいがちな皮膚疾患といえます。
では実際に、粉瘤の放置にはどのようなリスクがあるのでしょうか。この記事では、以下の内容を解説しています。
- 粉瘤の概要
- 粉瘤を取らずに放置するリスク
- 粉瘤の治療について
この記事を読むことで、粉瘤に対する正しい知識が身に付き、適切な治療を受ける決心ができるようになります。皮膚に粉瘤ができてお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.そもそも粉瘤とは?
粉瘤(ふんりゅう)は、皮膚の下にできる良性の嚢胞性病変で、表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)とも呼ばれます。皮膚の一部が袋状になり、その中に角質や皮脂などが溜まることで形成される良性の腫瘍です。
主に顔や首、背中など皮脂腺が多い部位に発生し、触れると柔らかく、中央に小さな開口部が見られることがあります。
関連記事:粉瘤とは?できやすい人の特徴はある?治療方法や予防法なども解説
1-1.粉瘤ができる原因
粉瘤の主な原因は、皮膚の外傷や毛穴の閉塞などによって、表皮細胞が皮膚内部に取り込まれ、増殖することです。これにより、内部に角質や皮脂が溜まり、嚢胞が形成されます。
また、遺伝的要因やホルモンバランスの乱れも関与していると考えられています。具体的な原因は完全には解明されていませんが、日常的に皮膚をケアし清潔を保つことが予防につながるとされています。
1-2.粉瘤の症状
粉瘤は初期段階では小さなしこりとして現れ、痛みや痒みはほとんどありません。しかし、時間が経つにつれて徐々に大きくなり、炎症を起こすと赤く腫れて痛みを伴うことがあります。
また、放置すると感染が広がり、周囲の組織に影響を及ぼす可能性があるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
2.粉瘤を取らずに放置するリスク
粉瘤を放置して取らないままにすることには、以下のようなリスクがあります。
- 徐々に肥大化していく
- 炎症が起きる
- 悪性化する
- 膿が溜まりにおいが強くなる
- 皮膚に跡が残る
- 血流の悪化や神経の圧迫が起きる
それぞれ解説していきます。
2-1.徐々に肥大化していく
粉瘤は放置すると、時間とともに大きくなる傾向があります。初期段階では小さな膨らみですが、放置することで徐々に肥大化し、目立ってしまう可能性があります。
顔や首など外から見える部位にできた粉瘤であれば、十分に注意しなければならないリスクです。
関連記事:
2-2.炎症が起きる
粉瘤を放置すると、細菌感染により炎症を引き起こすリスクが高まります。(炎症性粉瘤)
炎症が起こると、患部が赤く腫れ、痛みや熱感を伴います。さらに、膿が溜まることで膿瘍を形成し、症状が悪化することも。日常生活に支障をきたすだけでなく、治療も複雑化する可能性があります。
関連記事:赤い粉瘤は炎症性粉瘤かも!炎症性粉瘤の症状や原因・放置するリスクとは?
2-3.悪性化する
粉瘤は通常、良性の皮膚腫瘍ですが、まれに悪性化するケースも報告されています。放置した粉瘤が悪性腫瘍に変化するリスクは低いものの、完全には否定できないということです。
そのため、長期間放置せず、早めに医師の診察を受けることが重要です。
2-4.膿が溜まりにおいが強くなる
粉瘤が感染や炎症を起こすと、内部に膿が溜まり、悪臭を放つことがあります。
膿が皮膚表面に排出されると、衣服や周囲ににおいが移る可能性があり、衛生面や生活面に支障をきたすでしょう。
関連記事:【医師監修】粉瘤が臭くなる原因とは?においを解消する方法
2-5.皮膚に跡が残る
炎症や感染を繰り返した粉瘤は、治癒後に皮膚に跡が残ることがあります。特に、自己判断で圧迫したり、無理に排出しようとすると、傷跡や色素沈着が生じるリスクが高まります。
外からの見た目を損なわないためにも、適切な医療機関での治療が重要です。
2-6.血流の悪化や神経の圧迫が起きる
大きく成長した粉瘤は、周囲の血管や神経を圧迫することがあります。
これにより、血流が悪化したり、患部のしびれや痛みを引き起こしたりする可能性があり、注意しなければなりません。
3.粉瘤は放置せず治療しよう
粉瘤は、放置せずなるべく早く治療することで、炎症や悪化のリスクを抑え状態を改善することが可能です。ここからは、具体的な粉瘤の治療について解説していきます。
3-1.粉瘤は絶対に自分で取らない
粉瘤を治したいと考えたときに、自分で取ろうとしてしまう方が一定数いらっしゃいますが、絶対にやめてください。
たとえば針や刃物で粉瘤を刺したり、内容物を絞り出したりすることで、感染症や炎症を引き起こす可能性が高く、症状を余計に悪化させてしまいます。また、適切に嚢胞を除去できないと、再発の原因にもなります。
粉瘤が気になる場合は、自己判断で処置せず、必ず専門の医師に相談し、適切な治療を受けるようにしましょう。
関連記事:粉瘤を自分で潰すとどうなる?リスクや治し方について解説
3-2.粉瘤の治療法
粉瘤は、形成外科もしくは皮膚科にて治療を受けることが可能です。粉瘤の治療法として2つの方法をご紹介します。
3-2-1.治療法①切開法
切開法は、粉瘤の標準的な治療法で、粉瘤の上部を紡錘形に切開し、嚢胞全体を摘出する方法です。
切開法は局所麻酔下でおこなわれ、粉瘤の大きさに応じて皮膚を切開し、嚢胞とその内容物を完全に取り除きます。基本的に日帰りが可能で、約1~2週間後に切開部の抜糸をすれば完了です。
切開法は再発リスクが低いとされている治療法ですが、切開部が大きくなるため、傷跡が目立つ可能性があり注意が必要です。
3-2-2.治療法②くりぬき法
くり抜き法は、切開法同様に局所麻酔下でおこなわれ、円筒状の特殊なメスによって粉瘤の中心部に小さな穴を開け、内容物と嚢胞を取り除く方法です。また切開部が小さいため、傷跡が目立ちにくいのが特徴です。手術時間は短く、日帰り手術が可能です。
ただし、嚢胞を完全に取り除けない場合は再発のリスクがあります。また、粉瘤が大きい場合や炎症を起こしている場合には、この方法が適さないこともあります。
3-3.粉瘤の治療費用目安
粉瘤の治療費用は、治療方法や病院によって異なりますが、以下が一般的な目安です。
|
粉瘤の大きさ(非露出部) |
3割負担 |
1割負担 |
|
3cm未満 |
約4,000~5,000円 |
約1,500円 |
|
3cm~6cm未満 |
約10,000~12,000円 |
約3,500円 |
|
6cm〜12cm |
約12,000~14,000円 |
約4,500円 |
|
12cm以上 |
約25,000円 |
約8,000円 |
一般的に、粉瘤の摘出手術は保険適用となり、自己負担額は数千円から1万円程度が目安です。ただし、粉瘤の大きさや部位、手術の難易度によって費用は変動します。
また、初診料や検査費用、術後の処置費用なども別途かかる場合があるため、気になる方は各医療機関へ問い合わせてみてください。
3-4.粉瘤の治療における注意点
粉瘤の治療では、以下の3点に注意してください。
- 血液をサラサラにする薬を服用している場合は医師に相談する
- 治療による副作用がある
- 手術当日は血流が良くなる行動はしない
詳しく解説します。
3-4-1.血液をサラサラにする薬を服用している場合は医師に相談する
抗凝固薬や抗血小板薬などの「血液をサラサラにする薬」を服用している場合、手術中や術後に出血のリスクが高まる可能性があります。
そのため、これらの薬を服用している方は、手術前に必ず医師に伝え、適切な指示を受けるようにしましょう。
3-4-2.治療による副作用がある
粉瘤の摘出手術は一般的に安全とされていますが、手術には以下のような副作用や合併症のリスクが伴います。
|
感染症 |
手術部位が感染し、腫れや痛み、発熱などの症状が現れることがあります。 |
|
出血 |
手術中や術後に出血が起こる可能性があります。 |
|
瘢痕(はんこん) |
手術跡が残ることがあります。 特に大きな粉瘤や深部にある場合、傷跡が目立つことがあります。 |
これらのリスクを最小限に抑えるためには、医師から受ける手術前後の指示を守り、適切なケアをおこなうことが大切です。
3-4-3.手術当日は血流が良くなる行動はしない
手術当日は、出血や腫れを防ぐために、血流が良くなる行動を避けることが重要です。具体的には、以下のような行動を控えてください。
- 手術当日はシャワー程度にとどめ、湯船に浸かるのは避ける
- ランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動は控える
- 飲酒をしない
これらの行動を避けることで、術後の合併症を予防し、傷口の早期回復につながります。
4.まとめ
粉瘤の放置には、以下のようなリスクがあります。
- 徐々に肥大化していく
- 炎症が起きる
- 悪性化する
- 膿が溜まりにおいが強くなる
- 皮膚に跡が残る
- 血流の悪化や神経の圧迫が起きる
粉瘤は放置すればするほど悪化する可能性が高いため、形成外科や皮膚科といった専門の医療機関にて、できるだけ早めに治療を受けるようにしてください。
浅草橋西口クリニックMoでは、粉瘤をはじめとしたさまざまな皮膚疾患に対しての診療をおこなっています。「皮膚にできものができた」「炎症が起きて痛い」などのお悩みがある方は、ぜひ一度当院へご相談ください。
頴川博芸 エガワ ヒロキ 浅草橋西口クリニックMo 【経歴】 【資格・所属学会】
2016年 東海大学医学部医学科 卒業
2016年 順天堂大学医学部附属静岡病院 臨床研修医室
2017年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 入学
2018年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器・低侵襲外科
2021年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 修了
2021年 越谷市立病院 外科
2022年 順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科・消化器外科
2023年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科
2024年 浅草橋西口クリニックMo院長就任
日本専門医機構認定 外科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本旅行医学会 認定医
東京都認知症サポート医
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本温泉気候物理医学会
日本腹部救急医学会
日本大腸肛門病学会
順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科 非常勤医師
難病指定医
小児慢性特定疾病指定医