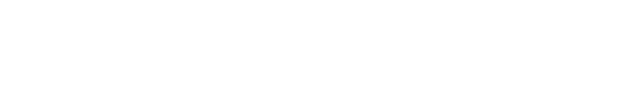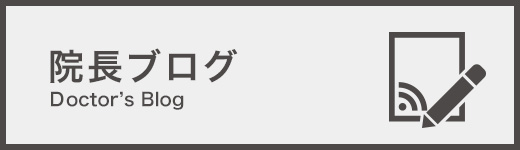首に粉瘤ができたらどうする?治療法や治療後の注意点
「首にしこりみたいなものができている」と思ったら、それは粉瘤かもしれません。
実際粉瘤は首にできやすいとされており、放置することで大きくなったり炎症を起こしたりすることもあります。首にできた粉瘤の見た目が気になってくる前に、正しく治療をおこなうことが重要です。
そこでこの記事では、以下の内容を解説しています。
- 粉瘤の概要について
- 首に粉瘤ができやすい理由として考えられるもの
- 首にできた粉瘤の治療法
- 首にできた粉瘤の治療後の注意点
コラムの最後には、粉瘤以外の首にできやすい皮膚疾患についても解説しています。首にできたしこりでお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.粉瘤とは?
粉瘤(ふんりゅう)は、皮膚の下にできる良性の嚢胞性腫瘍で、表皮嚢腫とも呼ばれます。皮膚の一部が袋状になり、内部に角質や皮脂がたまることで発生するのです。
通常痛みはありませんが、放置すると炎症や感染を引き起こす可能性があり、基本的には早期の治療をおすすめしています。
関連記事:粉瘤とは?できやすい人の特徴はある?治療方法や予防法なども解説
2.首には粉瘤ができやすい
粉瘤ができる原因は、はっきりとは解明されていないのが現状です。そんななか、首は比較的粉瘤ができやすい部位といわれています。
2-1.首に粉瘤ができやすい理由として考えられるもの
首に粉瘤ができやすい理由として考えられるのは、以下の3点です。
- 皮脂腺が多いから
- 衣服やアクセサリーなどによる摩擦や刺激を受けやすいから
- 汗をかきやすいから
それぞれ解説します。
2-1-1.理由①皮脂腺が多いから
首は皮脂腺が多く、皮脂の分泌が活発であることが挙げられます。
皮脂の分泌が多いと、毛穴が詰まりやすくなり、粉瘤の発生につながる可能性が高いです。
2-1-2.理由②衣服やアクセサリーなどによる摩擦や刺激を受けやすいから
首は衣服やアクセサリーなどによって、摩擦や刺激を受けやすい部位でもあります。これらの外的要因が皮膚に影響を与え、粉瘤の形成を促進することがあります。
2-1-3.理由③汗をかきやすいから
首は汗をかきやすく、湿度が高くなりがちな部位です。汗をかいたあとの皮膚は細菌の繁殖が起こりやすく、粉瘤のリスクが高まると考えられます。
2-2.首以外に粉瘤ができやすい部位
首以外にも、粉瘤ができやすい部位はいくつかあります。たとえば以下のような部位です。
これらの部位も皮脂腺が多く、摩擦や刺激を受けやすいため、粉瘤が発生しやすいとされています。
3.首にできた粉瘤は放置しない
首にできた粉瘤は、放置せずに適切な治療を受けることが重要です。放置すると、粉瘤が徐々に大きくなり、炎症や感染を引き起こす可能性があります。
特に首は目立つ部位であり、粉瘤が大きくなると見た目にも影響を及ぼします。また、炎症が進行すると痛みや発熱を伴うこともあり、日常生活に支障をきたす恐れも。
したがって、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
関連記事:粉瘤を治療せず放置するリスクとは?取らないとどうなるのか
4.首にできた粉瘤の治療法
粉瘤の治療法には、主に「くり抜き法」と「切開法」の2つがあり、粉瘤の大きさや状態によって適切な方法が選択されます。
医師と相談し、自分に合った治療法を選ぶことが重要です。
4-1.くりぬき法
くり抜き法は、粉瘤の中心部に小さな穴を開け、内容物と袋を取り除く手術方法です。この方法は、傷跡が小さく、術後目立ちにくいというメリットがあります。
手術時間も比較的短く、通常は縫合を必要としません。ただし、袋を完全に取り除けない場合、再発のリスクがあるため注意が必要です。
4-2.切開法
切開法は、粉瘤の大きさに合わせて皮膚を紡錘形に切開し、粉瘤全体を摘出する方法です。切開法は、粉瘤を確実に取り除くことができるため、再発のリスクが低いとされています。
ただし、くり抜き法に比べて傷跡が大きくなる点には注意しなければなりません。また、手術後は縫合が必要で、手術から1~2週間程度で抜糸をおこなう必要があります。
5.首にできた粉瘤の治療後の注意点
首にできた粉瘤の治療後は、適切なケアと注意が必要です。以下3つの注意点を確認してください。
- 手術後の傷口は清潔に保ち、医師の指示に従って定期的に消毒やガーゼ交換をおこなう
- 手術当日はシャワーで済ませ、患部を濡らさないようにする
- 首に負担がかかるような過度な動作やストレッチは避け、傷口への負担を最小限に抑える
万が一、傷口に異常や痛み、腫れが生じた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
6.首にできる粉瘤以外の皮膚疾患
首にできた膨らみが、粉瘤以外の皮膚疾患である場合も考えられます。
ここでは、粉瘤と似ていてかつ首にできやすい代表的な皮膚疾患として、ニキビと脂肪腫の特徴をご紹介します。
6-1.ニキビ
ニキビは、毛穴が皮脂や角質で詰まり、炎症を起こすことで発生します。首の後ろや顎のラインなど、皮脂分泌が活発な部位にできやすい傾向があります。
初期段階では小さな赤い丘疹として現れ、悪化すると膿が溜まることもあります。ストレスやホルモンバランスの乱れ、生活習慣などが原因とされ、適切なスキンケアや生活習慣の見直しが予防と改善に重要です。
関連記事:顔にできたできものはニキビじゃない?ニキビ以外のできものについて徹底解説
6-2.脂肪腫
脂肪腫は、皮下脂肪組織から発生する良性の腫瘍で、首や肩、背中などに柔らかいしこりとして現れます。通常、痛みはなく、ゆっくりと大きくなる傾向があります。
粉瘤と異なり、中央に黒い点はなく、内容物が排出されることもありません。放置しても問題ない場合が多いですが、見た目や大きさが気になる場合は、医師に相談して適切な処置を受けるようにしましょう。
関連記事:粉瘤の見分け方とは?粉瘤とニキビ・イボ・せつ・脂肪腫・痔ろうの違い
7.まとめ
いかがでしょうか。以下のような理由から、首には粉瘤ができやすいと考えられています。
- 皮脂腺が多いから
- 衣服やアクセサリーなどによる摩擦や刺激を受けやすいから
- 汗をかきやすいから
首にできた粉瘤を放置することで、肥大化や炎症が起き、日常生活に支障をきたす可能性も考えられます。そのためできるだけ早めに医療機関を受診し、治療を進めるようにしてください。
浅草橋西口クリニックMoでは、粉瘤をはじめとしたさまざまな皮膚疾患に対しての診療をおこなっています。「皮膚にできものができた」「炎症が起きて痛い」などのお悩みがある方は、ぜひ一度当院へご相談ください。
頴川博芸 エガワ ヒロキ 浅草橋西口クリニックMo 【経歴】 【資格・所属学会】
2016年 東海大学医学部医学科 卒業
2016年 順天堂大学医学部附属静岡病院 臨床研修医室
2017年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 入学
2018年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器・低侵襲外科
2021年 順天堂大学大学院医学研究科医学専攻(博士課程) 修了
2021年 越谷市立病院 外科
2022年 順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科・消化器外科
2023年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科
2024年 浅草橋西口クリニックMo院長就任
日本専門医機構認定 外科専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本旅行医学会 認定医
東京都認知症サポート医
日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会
日本温泉気候物理医学会
日本腹部救急医学会
日本大腸肛門病学会
順天堂大学医学部附属順天堂医院 食道・胃外科 非常勤医師
難病指定医
小児慢性特定疾病指定医