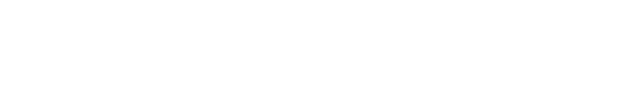糖尿病の原因や予防する方法とは?糖尿病になりやすい人の特徴まで解説
「糖尿病の原因やリスク要因は?」「生活習慣でできる糖尿病の予防策が知りたい」と思っていませんか?
糖尿病の人のほとんどは2型糖尿病で、その原因は「栄養バランスの摂れた食事」「無理のない適切な運動」「そのほかの生活習慣の改善」によって予防できます。
この記事では、糖尿病の原因や予防する方法、糖尿病になりやすい人の特徴まで紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
1.糖尿病のタイプ別の原因とは?
糖尿病のタイプ別の原因について紹介していきます。
- 糖尿病とは
- 糖尿病の原因
- 糖尿病の予防が重要な理由
それぞれ解説します。
1-1.糖尿病とは
糖尿病は、血液中のブドウ糖・血糖値が慢性的に高くなる病気です。食事から摂取した糖はインスリンの働きで体のエネルギーに変わります。
もしインスリンが不足したり働きが悪くなったりすると、糖はエネルギーとして使われず血液中にあふれ、血糖値が高い状態が継続します。血糖値を下げるホルモンであるインスリンの機能不全が、血糖値の慢性的な上昇を招きやすいです。
1-2.糖尿病の原因
糖尿病の原因は、以下によって異なります。
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
ひとつずつ解説します。
1-2-1.1型糖尿病
1型糖尿病は、自己免疫反応の異常が原因です。何らかの理由で免疫システムが膵臓のインスリンを作るβ細胞を攻撃します。
β細胞が破壊された場合、体内でインスリンはほとんど、またはまったく作れなくなります。生活習慣とは無関係に発症するため、本人の生活習慣を問わず、インスリン分泌細胞の破壊が発症を引き起こす病気です。
1-2-2.2型糖尿病
2型糖尿病は、遺伝的要因と生活習慣が重なり発症します。遺伝的に糖尿病になりやすい体質の人は、過食や運動不足、肥満といった要因にさらされやすいです。
また、それらの要因はインスリンの分泌低下や効きの悪化を招きます。そして、日本の糖尿病患者の9割以上が2型糖尿病です。遺伝的素因と好ましくない生活習慣が、インスリンの働きを悪化させ発症に至らせます。
1-3.糖尿病の予防が重要な理由
糖尿病の予防は、深刻な合併症を防ぐうえで極めて重要です。糖尿病自体には、初期症状がほとんどありませんが、もし高血糖の状態が続くと全身の血管が傷つきます。
また、細い血管の損傷は、失明や腎不全に至る「三大合併症」を引き起こす場合もあります。自覚症状のない進行は、命に関わる病気を招くリスクがあるため、事前の対策が何よりも大切です。
2.糖尿病になりやすい人の特徴
糖尿病になりやすい人の特徴を以下にまとめました。
- 家族に糖尿病患者がいる
- 家族で肥満や心血管系の疾患(脳卒中、心臓病など)がある人がいる
- 甘い食べ物や脂質の多い食事を好む
- 日常生活での運動が少なく、移動も自動車の使用が多い
- 頻繁に外食をする
- 体重が重い(肥満体型)
- 定期的にアルコールを摂取する
- ストレスを受けやすい生活環境にいる
提示した特徴に当てはまらない生活が、糖尿病予防につながります。詳しくは以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:糖尿病になりやすい人の特徴とは?糖尿病を予防する方法7選
3.糖尿病を予防する方法【食事・運動・生活習慣別】
糖尿病を予防する方法を、以下3つに分けて紹介していきます。
- 食事で気を付けるポイント
- 運動で気を付けるポイント
- その他の生活習慣で見直すべきポイント
それぞれ解説します。
3-1.食事で気を付けるポイント
食事で気を付けるポイントは、以下6つです。
- 1日3食なるべく決まった時間に食べる
- 主食・主菜・副菜をバランス良くそろえる
- 食物繊維が豊富な「野菜・きのこ類」から先に食べる
- ゆっくりよく噛み、腹八分目を心がける
- 糖質や塩分の摂りすぎに注意する
- 間食をとる場合は時間と内容を工夫する
ひとつずつ解説します。
3-1-1.1日3食なるべく決まった時間に食べる
食事を決まった時間に摂ることは、血糖値の安定につながります。たとえば、食事を抜くと次の食事で血糖値が急上昇しやすいです。
空腹時間が長くなった場合、体は栄養を過剰に吸収しようとします。そのため、朝食を抜くと昼食後と夕食後の血糖値が高くなります。この血糖値の乱高下を防ぐためには、1日3回の食事を規則的に摂る習慣が有効です。
3-1-2.主食・主菜・副菜をバランス良くそろえる
主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事は、糖尿病予防の基本です。各栄養素は、体内で異なる働きをするため、多様な食品の組み合わせが栄養の偏りを防ぎます。
また、主食・主菜・副菜の3つをそろえると、血糖値の上昇は緩やかになりやすいです。栄養バランスを整えるには、毎回の食事で3つの要素を意識することが推奨されます。
3-1-3.食物繊維が豊富な「野菜・きのこ類」から先に食べる
食事の最初に食物繊維が豊富な食品を食べると、血糖値の上昇を緩やかにできます。食物繊維は、糖の吸収を遅らせる働きを持ちます。
そのため、先に胃腸へ届くと、あとから入る糖質の吸収スピードを抑えやすいです。この食事法は「ベジタブルファースト」とも呼ばれ、血糖コントロールには野菜やきのこ類から食べ始める「食べ順」の実践が有効です。
3-1-4.ゆっくりよく噛み、腹八分目を心がける
ゆっくりよく噛む食事は、食べ過ぎを防ぎ、血糖値の上昇を抑えます。脳の満腹中枢は、食事開始から約20分で働き始めます。
しかし、早食いは満腹感を得る前に食べ過ぎる原因です。そのため、よく噛むと食事に時間がかかり適量で満足感を得やすくなります。満腹手前の「腹八分目」で食事を終えるには、時間をかけてよく噛む習慣が大切です。
3-1-5.糖質や塩分の摂りすぎに注意する
糖質と塩分の過剰摂取を避けることは、糖尿病予防に直結します。たとえば、糖質の多い食事は直接血糖値を上昇させるため、塩分の多い食事は、血圧を上げインスリンの働きを悪くするケースもあります。
とくに甘いお菓子やジュース、加工食品は、糖質や塩分を多く含む傾向が強いです。血糖値と血圧を適切に管理するには、糖質と塩分を控えた食生活の意識を持ちましょう。
3-1-6.間食をとる場合は時間と内容を工夫する
間食は、時間と内容を選ぶことで、血糖コントロールを妨げません。
空腹時間が長すぎると、次の食事で多めに食べてしまい、血糖値が急上昇する原因になります。そのため、間食は1日のエネルギー摂取量の1割程度、約200kcalが目安です。
また、糖質の少ないナッツ類を選び、血糖値が上がりにくい午後3時頃に摂るのがおすすめです。賢い間食には、食べるものとタイミングの工夫が求められます。
3-2.運動で気を付けるポイント
運動で気を付けるポイントは、以下3つです。
- エレベーターを階段にするなど日常生活の活動量を増やす
- ウォーキングなどの有酸素運動を取り入れる
- 筋力トレーニングを組み合わせる
それぞれ解説します。
3-2-1.エレベーターを階段にするなど日常生活の活動量を増やす
日常生活における活動量の増加は、手軽に始められる運動療法です。ただ、運動時間の確保は難しい場合もあるため、「ながら運動」を意識し、無理なく総消費カロリーを増やすのがおすすめです。
たとえば、エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなどは実践がしやすいでしょう。日々の暮らしで体を動かす機会を意図的に作り、活動的な生活を送ってください。
3-2-2.ウォーキングなどの有酸素運動を取り入れる
ウォーキングといった有酸素運動は、血糖値の改善に効果的です。有酸素運動は、ブドウ糖や脂肪をエネルギー源として消費してくれます。
食後1時間以内の運動は、食後血糖値の上昇を抑える効果が期待しやすいです。そのため、ややきついと感じる程度の速歩きを1回30分、週3〜5日おこなうのが良いでしょう。血糖コントロールと体力の向上には、継続的な有酸素運動の習慣化がおすすめです。
3-2-3.筋力トレーニングを組み合わせる
筋力トレーニングは、インスリンが効きやすい体を作ります。筋肉は、体内で最も多くのブドウ糖を消費する組織のため、筋肉量が増加すると基礎代謝が上がりブドウ糖が消費されやすくなります。
とくに、スクワットや腕立て伏せといった大きな筋肉を鍛えるトレーニングは効率的です。血糖値の安定には、有酸素運動に加えた筋力トレーニングの導入が有効です。
3-3.その他の生活習慣で見直すべきポイント
その他の生活習慣で見直すべきポイントは、以下3つです。
- 適正体重(BMI25未満)を目指して維持する
- 禁煙を実践し受動喫煙も避ける
- お酒は「適量」を知って上手に付き合う
- 質の良い睡眠を十分にとって心と体を休ませる
- 自分に合った方法でストレスを上手に発散する
ひとつずつ解説します。
3-3-1.適正体重(BMI25未満)を目指して維持する
適正体重の維持は、糖尿病予防の重要な目標です。BMI25以上の肥満(内臓脂肪の増加)は、インスリンの働きを妨げる物質を分泌させます。この分泌された物質が、インスリン抵抗性の主な原因です。
BMIの計算方法=体重kg ÷(身長m × 身長m)
そのため、インスリンの働きを良くするには、BMI25未満を目標にした体重コントロールが大切です。
3-3-2.禁煙を実践し受動喫煙も避ける
禁煙は、糖尿病のリスクを減らすうえで不可欠です。
喫煙は、交感神経を刺激し血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促しやすく、インスリンの効きを悪くします。そのため、喫煙者は非喫煙者と比較し糖尿病リスクが高くなる傾向にあります。
自身と周囲の人の健康を守るためには、禁煙の実践と受動喫煙を避ける環境作りが重要です。
3-3-3.お酒は「適量」を知って上手に付き合う
飲酒は、適量を守ることが糖尿病予防で重要です。とくにアルコールの過剰摂取は、すい臓にダメージを与えインスリン分泌を低下させる場合もあります。また、おつまみによるカロリー過多も問題になります。
1日の適切な飲酒量は、純アルコール換算で20g程度です。お酒を楽しむ際は、自身の「適量」を把握し、飲み過ぎない心がけが求められます。
3-3-4.質の良い睡眠を十分にとって心と体を休ませる
十分で質の良い睡眠は、血糖コントロールに良い影響を与えます。たとえば、睡眠不足は食欲を増進させるホルモンを増やし食欲を抑えるホルモンを減らすため、血糖値を上げるホルモンの分泌も促進します。そのため、1日7時間程度の睡眠をとる人は、糖尿病発症リスクが低いです。心と体の健康を保ち糖尿病を予防するためには、質の高い睡眠確保が大切です。
3-3-5.自分に合った方法でストレスを上手に発散する
ストレスの上手な管理は、糖尿病予防につながります。ストレスを感じると、体は血糖値を上昇させるホルモンを分泌し、慢性的なストレスは高血糖の原因です。
また、ストレスによる過食や飲酒も血糖コントロールを乱す一因です。血糖値を安定させるには、自分なりのストレス解消法を見つけ心身のバランスを整えましょう。
4.糖尿病予防の成功には定期的に健康診断を受けるのが大切
定期的な健康診断は、糖尿病予防の効果測定と早期発見に不可欠です。糖尿病は、自覚症状がないまま進行しやすいです。生活習慣の改善努力の効果は、客観的な数値での確認が必要です。健康診断の血液検査は、空腹時血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)といった項目で、体の状態を把握できます。自身の状態を把握し予防への意欲を保つためには、年一回の健康診断受診が重要です。
5.まとめ
糖尿病の多くは、生活習慣の見直しで予防できます。とくに2型糖尿病は、日々の生活習慣の積み重ねが大きく影響しており、食事や運動、生活習慣などの見直しで発症リスクを大幅に下げられます。
浅草橋西口クリニックMoでは、糖尿病をはじめとしたさまざまな疾患に対しての診療をおこなっています。「糖尿病で生活が変化しないか不安」「早いうちから糖尿病を予防したい」などのお悩みがある方は、ぜひ一度当院へご相談ください。