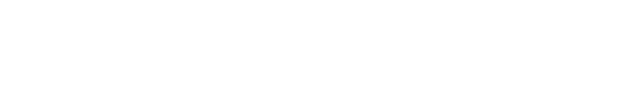糖尿病にならないために気を付けるべき習慣とは?防ぐコツまで解説
「糖尿病にならないためにはどうしたら良い?」「糖尿病を予防するための具体的な生活習慣の改善方法を知りたい」「食事や運動で気をつけるポイントを把握したい」と思っていませんか?
糖尿病にならないためには、バランスの取れた食事や無理のない運動、十分な休養といった毎日の小さな心がけの積み重ねが重要です。
この記事では、糖尿病にならないために気を付けるべき習慣や防ぐコツまで紹介します。
糖尿病の予防について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.糖尿病とは
糖尿病とは、インスリンの働きが悪くなり、血液中の糖分の値が慢性的に高くなる病気です。そのため、以下の観点から病気を正しく理解するのが重要です。
- 糖尿病の基本的な仕組み
- 糖尿病の主な初期症状
- 糖尿病の種類
- 糖尿病を引き起こす主な原因
- 症状を放置した場合の深刻な影響(三大合併症)
それぞれ解説します。
1-1.糖尿病の基本的な仕組み
インスリンの作用不足で血液中のブドウ糖が細胞にうまく取り込まれなくなる状態が、糖尿病の基本的な仕組みです。
食事で摂取した糖は、通常インスリンの働きで細胞のエネルギー源となります。そのため、インスリンの分泌量が減る、または働きが悪くなるとブドウ糖が血液中に溢れやすいです。
健康な人の体は、インスリンが血糖値を常に適切な範囲にコントロールします。血糖値を正常に保つ体のメカニズムが、機能しなくなる状態が糖尿病です。
1-2.糖尿病の主な初期症状
糖尿病の主な初期症状は、以下のとおりです。
- 喉の渇き
- 頻繁なトイレ
- 急な体重減少
- 疲れやすさ
高血糖の状態では、体は余分な糖を尿と一緒に排出しようとします。過程で多くの水分が失われるため、脱水症状になり喉が渇きやすいです。
また、エネルギー源のブドウ糖が細胞に届かないと、体重減少や倦怠感も現れます。初期症状のサインを見過ごさず、自身の体調変化に注意を払うのが大切です。
関連記事:【医師監修】糖尿病の初期症状とは?放置するとどうなる?
1-3.糖尿病の種類
糖尿病には、主に「1型」と「2型」の2つのタイプが存在します。しかし、生活習慣病としての糖尿病は、主に「2型糖尿病」です。
「1型」は、自己免疫疾患などでインスリンを分泌する膵臓の細胞が壊れて発症します。対して「2型」は、遺伝的要因に加え、過食や運動不足、肥満といった生活習慣が原因で発症します。生活習慣の見直しで、予防・改善が期待できる点が「2型糖尿病」の特徴です。
1-4.糖尿病を引き起こす主な原因
糖尿病発症の主な原因は、遺伝的な要因に加え、「肥満」「過食」「運動不足」「ストレス」などの生活習慣の乱れです。とくに内臓脂肪が増えるタイプの肥満は、インスリンの働きを悪くする大きな要因です。
また、高カロリー・高脂肪な食事や体を動かさない生活は、血糖値をコントロールする体の仕組みに負担をかけます。さらに、精神的なストレスも血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促します。
日々の生活スタイルが、糖尿病のリスクに直結していると理解することが必要です。
1-5.症状を放置した場合の深刻な影響(三大合併症)
糖尿病を治療せず放置すると、深刻な合併症を引き起こす危険性が高まります。高血糖は、全身の細い血管を傷つけ、合併症はゆっくりと確実に進行します。
代表的な三大合併症は、「網膜症」「腎症」「神経障害」です。網膜症は失明に、腎症は人工透析に、神経障害は足の壊疽や切断につながるリスクもあります。
自覚症状がないと安心せず、合併症の恐ろしさを認識し、早期から対策を講じることが極めて重要です。
2.糖尿病にならないために気を付けるべき6つの生活習慣
糖尿病にならないために気を付けるべき生活習慣は、以下の6つです。
- 栄養バランスを考えた食事を摂る
- 無理なく続けられる運動を習慣にする
- 食事と運動で適正体重を維持する
- 質の良い睡眠を十分にとる
- 禁煙を徹底してお酒は適量を守る
- 自分に合った方法でストレスを管理する
ひとつずつ解説します。
2-1.栄養バランスを考えた食事を摂る
健康な体づくりの基本は、栄養バランスの取れた食事を摂ることです。主に「主食・主菜・副菜」をそろえると、体に必要な栄養素を過不足なく摂取できます。
具体的には、ご飯やパンなどの「主食」、肉や魚などの「主菜」、野菜やきのこなどの「副菜」を意識的に食卓に並べましょう。多くの品目を食べることは、血糖値の急激な上昇抑制にもつながります。特定の食品を制限せず、多様な食材をバランス良く楽しむ食生活の心がけが重要です。
2-2.無理なく続けられる運動を習慣にする
血糖値の安定には、継続的な運動が効果的です。運動は血液中のブドウ糖を筋肉で消費させ、インスリンの働きを良くする効果が期待できます。
激しいトレーニングは不要なため、ウォーキングのような軽めの運動でも十分意味があります。大切なのは、無理なく楽しみながら続けられる運動を見つけることです。
日常生活のなかに運動を取り入れる工夫をすると、健康的な習慣として定着させやすいです。
2-3.食事と運動で適正体重を維持する
適切な食事管理と運動習慣によって、自分にとっての適正体重を維持するのが重要です。肥満、とくに内臓脂肪の増加は、糖尿病の最も大きな危険因子です。
もし体重が増加すると、インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」の状態に陥りやすくなります。そのため、BMIなどを参考に、自身の体重が適正範囲にあるか確認をしておきましょう。
体重のコントロールは、糖尿病予防の要であると認識しておくことが大切です。
2-4.質の良い睡眠を十分にとる
心身の健康維持には、質の良い十分な睡眠が不可欠です。睡眠不足は、食欲を増進させるホルモンを増やし、インスリンの働きを悪くします。
もし睡眠時間が短いと日中の眠気や集中力低下だけでなく、血糖コントロールにも悪影響をおよぼします。そのため、自分に合った睡眠時間を見つけ、寝室の環境を整えるなど安眠の工夫をしましょう。
健やかな眠りは、糖尿病を遠ざけるための大切な生活習慣です。
2-5.禁煙を徹底してお酒は適量を守る
喫煙や過度な飲酒は、血糖コントロールを乱す原因となり、厳しく管理する必要があります。たとえば、タバコに含まれるニコチンは、血糖値を上げるホルモンを刺激し、インスリンの働きを妨げます。
また、アルコールの過剰摂取はカロリーオーバーや、ほかの生活習慣の乱れにもつながりやすいです。禁煙を徹底し、お酒を飲む場合は適量を守る明確なルールを設けることが、健康管理の基本です。
2-6.自分に合った方法でストレスを管理する
現代社会でストレスを完全になくすことは困難なため、自分に合った方法で、上手に管理するのが大切です。過度なストレスは、血糖値を上昇させるホルモンの分泌につながります。
ストレスを感じると体は、「コルチゾール」や「アドレナリン」を分泌します。分泌されるホルモンには血糖値を上げる作用があり、慢性的なストレスは糖尿病のリスクを高めやすいです。そのため、趣味に没頭する時間や、リラックスできる習慣を持っておくのが心と体の健康を守ります。
3.糖尿病にならないためには食事管理が大切
糖尿病にならないためには、以下のような食事管理が大切です。
- 規則正しく1日3食を意識する
- 血糖値の急上昇を防ぐ「ベジファースト」を徹底する
- 主食は控えめに食物繊維が豊富な食材を積極的に選ぶ
- 「蒸す・茹でる」を活用して賢くカロリーダウン
- 糖分の入った飲み物をやめて水やお茶を基本にする
それぞれ解説します。
3-1.規則正しく1日3食を意識する
食事を抜くと次の食事で血糖値が急上昇しやすくなるため、1日3食を規則正しく摂ることが基本です。
もし空腹の時間が長くなると、体は飢餓状態と認識し、次の食事で栄養を溜め込もうとします。食後の血糖値が急激に上がるため、インスリンを分泌する膵臓にも負担がかかりやすいです。
そのため朝食を抜かず、なるべく毎日同じ時間帯に食事を摂ることを心がけましょう。規則正しい食生活のリズム作りが、血糖値の安定につながります。
3-2.血糖値の急上昇を防ぐ「ベジファースト」を徹底する
食事の最初に野菜やきのこ類を食べる「ベジファースト」は、血糖値の急上昇抑制に効果的です。たとえば、食物繊維を多く含む食品を先に食べると、あとから食べる糖質の吸収が穏やかになります。
そのため食事の際は、まず野菜の小鉢やサラダから手をつける習慣をつけましょう。また、食物繊維は満腹感を得やすくする効果もあり、食べ過ぎの防止にも役立ちます。
3-3.主食は控えめに食物繊維が豊富な食材を積極的に選ぶ
ご飯やパンなどの主食の量を少し意識し、代わりに食物繊維が豊富な食材を選ぶのが望ましいです。
主食に含まれる糖質は、血糖値を直接上げる主な原因です。完全に抜く必要はありませんが、量を普段の8割程度に調整するだけでも効果があります。
具体的には、白米を玄米や雑穀米に変えたり、野菜やきのこ、海藻類を積極的に食事に取り入れたりしましょう。賢い食材選びで満足感を保ちながら、糖質の摂取量をコントロールできます。
3-4.「蒸す・茹でる」を活用して賢くカロリーダウン
「揚げる」「炒める」といった油を多く使う調理法より、「蒸す」「茹でる」調理法を選ぶと摂取カロリーを賢く抑えられます。
調理油は、少量でも高カロリーで肥満の原因となりやすいです。鶏肉を唐揚げにせず蒸し鶏にするだけでも、大幅なカロリーダウンができます。
また、素材の味を活かす調理法は薄味にもつながり、塩分の摂りすぎを防ぐ効果も期待できます。調理方法の選択が、健康的な食生活を支える重要なポイントです。
3-5.糖分の入った飲み物をやめて水やお茶を基本にする
普段の水分補給は、水やお茶といった無糖の飲み物を基本にするのが大切です。たとえば、ジュースや加糖コーヒーなどの甘い飲み物には、想像以上に多くの糖分が含まれるため、液体に含まれる糖分は吸収が速く血糖値を急激に上昇させます。
また、清涼飲料水は「ペットボトル症候群」という急性糖尿病の原因になる場合もあります。喉が渇いたときに飲むものを変えるだけで、無意識に摂取していた糖分を大幅に減らせます。
4.糖尿病にならないために運動をしよう
糖尿病にならないためには、ポイントを抑えながらおこなう適度な運動が欠かせません。
- おすすめは「有酸素運動」と「筋力トレーニング」の組み合わせ
- 最適な運動のタイミング・頻度・時間の目安
- 運動を習慣化するためのポイント
ひとつずつ解説します
4-1.おすすめは「有酸素運動」と「筋力トレーニング」の組み合わせ
糖尿病予防には、「有酸素運動」と「筋力トレーニング」の組み合わせが効果的です。たとえば、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、運動中に血液中のブドウ糖を直接エネルギーとして消費します。
また、スクワットなどの筋力トレーニングは、筋肉量を増やして基礎代謝を上げ、インスリンが効きやすい体質を作りやすいです。有酸素運動で血糖を消費し、筋トレでインスリンの効率を上げる相乗効果が期待できます。そのため、両方をバランス良く取り入れる運動プラン作りが理想的です。
4-2.最適な運動のタイミング・頻度・時間の目安
運動は、食後の血糖値が上がり始める「食後30分から1時間以内」におこなうのが効果的です。タイミングの良い運動は、食事で増えた血液中のブドウ糖を効率良く消費できます。
運動の頻度は、できれば毎日、少なくとも週に3〜5日おこなうのが望ましいです。また、1回あたりの時間は「20分〜60分」、週に「合計150分以上」を目標にしましょう。ただし、無理のない範囲から始め、徐々に時間や頻度を増やしていくのが運動を継続させるコツです。
4-3.運動を習慣化するためのポイント
運動を三日坊主で終わらせないためには「ながら運動」を取り入れたり、仲間と一緒に取り組んだりすることが習慣化の助けになります。たとえば、テレビを見ながらストレッチをする、通勤時に一駅手前で降りて歩くのも良い方法です。
また、カレンダーに印をつけるなど、自分の頑張りを可視化することもモチベーション維持につながります。達成可能な小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねていくことが大切です。
5.糖尿病になりやすい人の特徴【セルフチェック】
糖尿病は特定の生活習慣や遺伝的背景を持つ人がなりやすい傾向にあります。自分に当てはまる項目がないか一度セルフチェックをしてみましょう。リスクの認識が生活習慣を見直す第一歩です。
- 家族に糖尿病患者がいる
- 家族で肥満や心血管系の疾患(脳卒中、心臓病など)がある人がいる
- 甘い食べ物や脂質の多い食事を好む
- 日常生活での運動が少なく、移動も自動車の使用が多い
- 頻繁に外食をする
- 体重が重い(肥満体型)
- 定期的にアルコールを摂取する
- ストレスを受けやすい生活環境にいる
多くの項目に当てはまるからといって、必ず糖尿病になるわけではありません。リスクが高いことを自覚し、早期に生活改善に取り組むことが将来の健康を守るうえでは重要です。
関連記事:糖尿病になりやすい人の特徴とは?糖尿病を予防する方法7選
6.糖尿病かも?と思ったら早めに医療機関で診察を受けよう
生活習慣の改善は糖尿病予防の基本のため、少しでも体に異変を感じたら速やかに医療機関を受診するのが重要です。もし初期症状に心当たりがある場合、自己判断で放置してはいけません。
具体的に、糖尿病の診断は血液検査などで血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の値を調べたうえで確定します。まずはかかりつけの内科、もしくは糖尿病内科や内分泌内科などの専門医に相談しましょう。糖尿病の早期発見・早期治療が、重篤な合併症を防ぐ最善策です。
関連記事;糖尿病かと思ったらどうする?初期症状や何科を受診すべきかなど解説
7.まとめ
糖尿病にならないための予防の鍵は、食事や運動、睡眠といった毎日の小さな心がけの積み重ねにあります。とくに「バランスの取れた食事」「無理のない運動」そして「十分な休養」が、血糖値を安定させ、健康な体の維持につながります。
浅草橋西口クリニックMoでは、糖尿病をはじめとしたさまざまな疾患に対しての診療をおこなっています。「糖尿病で生活が変化しないか不安」「早いうちから糖尿病を予防したい」などのお悩みがある方は、ぜひ一度当院へご相談ください。